4/8掲載 筑波大学 名誉教授 遠藤 誉 氏
――米ウォール街の人間はむしろ中国と仲良くしようとしている…。
遠藤 金融界はグローバルな流れがなければ発展しない。その代表格であるウォール街を牛耳っていたヘンリー・キッシンジャー元国務長官は中国ととても仲が良い。きっかけは、2000年に中国がWTOに加盟する際、当時国務院総理だった朱鎔基(しゅようき)が世界のスタンダードを知るために清華大学経済管理学院に顧問委員会を作り、米財界のトップ達を招き入れたことだった。米国ではキッシンジャー・アソシエイツ(コンサルタント会社)の門をくぐった大財閥が支配力を強めているが、そういった人物達が、当時、キッシンジャーを通して清華大学経済管理学院の顧問委員会へ送り込まれている。その結果、米国と清華大学に強いパイプが出来ているという訳だ。ちなみに、朱鎔基、胡錦涛、習近平らはいずれも清華大学出身であり、今では清華大学の経済管理学院にある顧問委員会は習近平政権の巨大なシンクタンクになっている。米国が中国に対して高関税という形で攻めたとしても、最後は習近平のお膝元にいる金融界や大財閥が動きを見せるだろう。水面下ではすでに手を握っている可能性もある。
――一方で、ハイテクの世界においては、中国は世界中から優秀な人材を集め、人材獲得競争では米国はすでにかなわない状況になりつつある…。
遠藤 中国の人材のネットワークたるや凄まじい。欧米に留学した300万人から成る中国人博士たちが帰国している。そして、そういった博士たちが、人類が絶対に解読できない量子暗号を搭載した人工衛星「墨子号」を打ち上げることに成功するなど目覚ましい成果を収めている。2018年にはオーストリアとタイアップして「墨子号」を介した量子通信に成功。そして、今年2月14日には「墨子号」打ち上げグループが量子通信成功により米国の科学賞「クリーブランド賞」を受賞。これは米国の科学界も中国の功績を認めたということであり、量子暗号の世界では中国がアメリカよりも一歩進んだことになる。さらに、月の裏側には地球から直接信号を送ることができないので、軟着陸するためには中継通信衛星が必要だが、中国は昨年5月に中継通信衛星「鵲橋(じゃっきょう)号」を打ち上げることにも成功している。月の周りに、引力も斥力も作用しないラグランジュ点と言われる「力が存在しない点」があるが、そこにピンポイントで「鵲橋号」を打ち当てることに成功し、その上で今年1月3日に月の裏側に軟着陸することに成功した。米国はその技術を持っていないため、「鵲橋号」を使用したいと中国に頼んできた。中国はそれを承認したのだが、その瞬間、中国と米国の宇宙での立場が逆転したと言っていいだろう。
――非民主的な国が世界を制覇するというのは歓迎しない…。
遠藤 唯一我々が出来ることは、中国を民主化させることだろう。民主化させるために手を貸すのであれば良いが、中国にとって世界制覇の手段である「一帯一路」構想には絶対に協力すべきではない。安倍総理は自分が国賓として正式に中国に招かれ、また習近平国家主席を日本に招くというシャトル外交を実現することにより自分の外交力を日本国民にアピールしたいという願望も手伝い、一帯一路への協力を承認した。2017年5月の国際フォーラムで、それまで手掛けていた「インド太平洋戦略」という素晴らしいアイディアを捨てて、一帯一路に協力することを中国側に表明した。一帯一路は他国を借金漬けにして借金を払えなければシーレーンの要衝である港湾を奪うという、中国による軍事戦略であり、かつ途上国に変わって人工衛星を打ち上げメインテナンスも中国がするという、宇宙の実効支配を目指す戦略でもある。また5Gに関して中国側を有利な方向に導き、世界の通信インフラを中国が牛耳ろうというデジタル・シルクロードであるということもできる。日本はその一帯一路に絶対に手を貸すべきではない。
4/22掲載 長崎大学核兵器廃絶研究センター 副センター長 教授 鈴木 達治郎 氏
――不必要な原発を廃炉にすることは可能なのか…。
鈴木 廃炉費用は引当金として積み立てられているが、本当にその積立金で足りるのかはわからない。従来40年だった引当期間は、福島事故の影響でそれより早い時期に廃炉が決定されるケースが出てきたため、法律改正によって廃炉を決定した後も引き続き積み立てすることが認められた。しかし、処分場もまだ決まっていないため、方法によってはコストが上がる可能性もある。原子力発電所は通常、最初に莫大な設備投資を行い、それを減価償却によって徐々に減らしていく。15年程度で設備費を完済し、その後の費用は運転費だけになる。つまり、電力会社としては古い原子炉ほど経済性が高い。安全性に関しては原子力規制委員会のチェックを受けて、その都度設備投資をすることになるが、その時の投資額と稼働を延長した場合の利益のバランスで廃炉にするかどうかが決まる。結局、これは電力会社の経営の問題だ。
――エネルギー資源の転換について何か良い案はないのか…。
鈴木 政府目標として原子力依存度を下げる事は掲げられているものの、具体的な政策は導入されていない。自治体としても原子力をやめれば交付金がなくなるといった財政事情があるため脱原発はなかなか難しい。脱炭素、脱原子力を本気で進めるのであれば、実際に原子力依存度を下げていくためのインセンティブが必要だ。再生可能エネルギーのポテンシャルも地道に研究開発を続ければまだまだあるはずだ。他方で、原発を作り続ける理由として核兵器の製造能力を確保するため、という見方もあるようだが、そのような論理では原子力を進める理由としては不適切であり、逆に国際的緊張を生む逆効果をもたらすので私は反対だ。
――核燃料デブリを30~50年間放置にしている間に、トリチウムを除去できるような革新的な技術が発明される可能性はないのか…。
鈴木 技術革新の可能性はもちろんあるが、今の技術のままでもリスクは十分に低い。ただ、結局のところは地元の方との信頼関係なのだと思う。いくら新しい技術が出来たとしても、その技術を信じられないから今も海洋放出が出来ていない。廃棄物処分の問題も同じだ。技術力だけで解決しようと思っても同じことの繰り返しになるだろう。今回の件については、まずは信頼関係を築くことが必要不可欠であり、そのためにはしっかりとした情報公開を行い、十分に議論することが重要だと思う。
5/7掲載 多摩大学大学院教授 ルール形成戦略研究所所長 國分 俊史 氏
――自民党が提言する国家経済会議(日本版NEC)の創設は、米中デジタル経済冷戦で激化するエコノミック・ステイトクラフトの応酬に日本が翻弄されない安全保障経済政策の司令塔として不可欠だ…。
國分 私はルール形成戦略の専門家として、常々、ルール形成のトレンドは安全保障経済政策、社会課題、技術革新を起点として捉えることが重要だと提唱している。しかし、日本ではこれまで「経済安全保障=石油のシーレーン確保」という非常に狭い概念であった他、ODAに至っては国連常任理事国入りを目指した友好国作りに主眼が置かれ過ぎてきており、そこには「他国の政策を日本の安全保障環境を改善させる方向へと促しつつ、日本企業の収益機会も増大させる安全保障経済政策」という概念が欠落していた。2014年から運用が開始された国家安全保障会議(NSC)は外務省と防衛省だけの構成で、中期的な安全保障政策の立案、防衛大綱の改定、武力攻撃事態への対応、重大緊急事態への対応が主となっている。NSCにより軍事的脅威に対する日本の安全保障政策のあり方を、他国と機密情報を共有して検討できるようになった点では大きく前進したと言えるが、日本企業の製品やサービス、オペレーションやバリューチェーンの裏に隠されている真の強みを梃子にした「他国に対する安全保障政策への展開を能動的に検討すること」はミッションには含まれていない。こうした前提の下で米中はデジタル経済冷戦に突入した。中国が激化させている経済力を圧力にして、相手国の安全保障政策を自国に有利なものへと変更させるエコノミック・ステイトクラフト(ES)への対抗政策の応酬が続くのが、これからの20年だ。米国はオバマ政権末期から中国のESに対抗するべく、国家経済会議(NEC)において経済制裁の強化策を構想してきた。トランプ政権下で政治任用のポジションの多くを空席にしながらも対米外国投資委員会(CFIUS)、米国輸出管理改革法(ECRA)、輸出管理規則(EAR)、国際武器取引規則(ITAR)の改定が迅速に進んできたのは、超党派による米中デジタル経済冷戦の構想が描かれてきた証左だ。米国は同盟国とこれまで以上に経済制裁の発動を増大していく予定であり、当然、日本に対しても日本独自の効果的な経済制裁の構想を期待してくることが予想される。しかし、日本はこれまで経済制裁を単独で自ら実施してきた歴史がなく、米国の経済制裁に従ってきただけだ。
――日本の利益を守り、平和を維持するためにも、外交の中で特定のポリシーメーカーの思考や行動を変化させるピンポイント型の経済制裁を構想できるような体制が必要だ…。
國分 経済大国第3位の日本の力でやれる経済制裁はたくさんあるし、それを考えて良いはずだ。対韓国のケースでも事前にいくつも経済制裁案を検討しておき、それを発動するか否かは政治判断で適宜決めれば良い。事前に相手国の議員や官僚など特定の政策決定者に関係する重要な企業や組織を特定しておき、如何にそこに対して効果的な経済制裁プランを検討できているかが重要ということだ。相手国の経済全体にダメージを与えるような経済制裁は戦争リスクを高めることから最終手段にすべきであり、まずはポリシーメーカーの急所に絞って発動することが、国家間の緊張を刺激することなく的確に影響を与える有効な手段となる。私は米国の経済制裁チームと話をする機会もあるが、彼らは「ピンポイントで経済制裁をして相手の考えを正すことによって、戦争など国家間の大きな問題への発展を止める」という意識を明確に持っている。最近の例で言えば、対ロシア制裁に違反したとして中国共産党中央軍事委員会で装備調達を担う装備発展部と、その高官1人を米独自の制裁対象に指定したと発表した。これにより、装備発展部は米国の金融システムから排除され、同部の高官は米国内の資産が凍結されると報道された。このように米国では、どの組織の誰をターゲットにすべきかというデザインが予め明確に描かれている。実は米国は東西冷戦崩壊後に、これからは軍事力ではなく経済力を梃子にした安全保障政策の展開の時代に入ると認識してNECを創設した。そして冷戦終結によって生まれたCIAの余剰キャパシティを使って、世界中の誰に経済制裁を行うことが一番効果的なのかを多面的に分析し、それを今日もアップデートし続けている。そしてエコノミック・ステイトクラフトという中国との経済戦争の本格化に向けて効果的な経済制裁の準備を進めてきている。ゆえに、「自由主義」に対しても日本とは認識が違う。日本では米国の動きを受けて関税引き上げ、数量規制の多用がブロック経済へと回帰させて戦争リスクを高めるという論調一色だ。しかし、こうした不安が生み出すボラティリティによって収益を得る金融ビジネスが巨大なセクターである米国からすれば、世界経済の不透明感の高まりは日本ほど深刻な話にはならない。ましてや自由主義経済論の始祖アダム・スミスが国富論の中で喝破している「国防は経済に優先する」という思想が浸透している米国においては、自由が生み出すバランスの崩壊が国防を脅かすようなら、バランスを取り戻すために一時的な保護主義は当然という前提も埋め込まれている。
7/8掲載 アクアスフィア・水教育研究所 水ジャーナリスト 橋本 淳司 氏
――昔はどこでも無料で飲めていた水が、今はお金がなければ飲めない時代になってきた…。
橋本 水道経営は厳しい。民営化されようと公営のままであろうと厳しい。今後、水道の持続性が危うい地域が出てくる。水道料金は水源地から蛇口までのコストを利用者数で割り決定されているため小規模集落にとっては高コストになる。将来さらに人口減少が進み、今よりも20倍程度水道料金が高くなるといわれている地域もある。今後そのような地域が増えていくと考えられる中、例えば、宮崎市内のある地区では、既に週に数回給水車が回り、受水タンクに給水を行っている。また、五島列島では雨水を生活水に活用し始めたり、岩手では住民でも簡易に管理できる浄水装置の実証実験を行うなど、自治体ごとの工夫がある。このように、大規模集中型の浄水場から24時間、鉄の管で水を提供するというこれまでの水道システムが終わる可能性が出てきている。
――自然の恵みである雨水を利用する。そのメリットは…。
橋本 雨水を貯留して活用することは、洪水の脅威を緩和するという部分もある。現在、雨水は下水道に流れて法律上も飲み水には適用できないようになっているが、本来、非常にきれいなものだ。各家庭で貯水槽を作り、家庭排水などとは別にして、きちんと貯めて使うという事を考えたほうが良い。特に東京都内では年間降水量の方が年間水道使用量よりも多く、周辺のダムから高コストの水を持ってくるよりも安く済む。また、今世紀末には東京の気温が屋久島並みになると言われているが、雨水を使うことで都市部の気温上昇を緩和することもできる。逆に言えば、そういったことをやらなければ、気温が上昇してくる中でアスファルトやコンクリートだらけの東京での暮らしは非常に厳しいものになるだろう。
――行政の対応と、水道民営化の問題点について…。
橋本 昨年、政府は水道法の一部を改正して水道の基盤の強化を打ち出したが、現場を見る限りそれを遂行できる体力はないように思う。行政の担当者がたった一人で水道事業を行っている自治体も多くあり、そもそも、きちんとした水道配管図が作られているところが6割程度しかない。配管図がないと事故が起きた時に修復のしようがないのに4割はそれがないということだ。人と財源はどうしても必要であり、今回の実行プランはその実現可能性をきちんと考えたうえで作られたのか疑問に思う。また、水道事業を民営化する欠点は、自治体に人とノウハウが残らないという事だ。例えば20年や30年の長期契約になれば、自治体側にはその後の事業契約を選択する権限はなくなり、あとは契約更新するだけになるだろう。その企業を買収するような体力もない。そうすると、水は企業のものになり、地域住民のものではなくなる。30年後にどのような街づくりをしていきたいのか、そのプラン作りを、今、しっかりと考えておく必要がある。
10/21掲載 外交戦略研究家 初代パラオ大使 貞岡 義幸 氏
――日本は韓国のプロパガンダに圧倒的に負けている…。
貞岡 日本と韓国のプロパガンダ(政治宣伝)の違いは、国民性に起因するところが大きい。島国で単一民族である日本には「沈黙は金」、「忖度」、「空気を読む」、「以心伝心」、「阿吽の呼吸」といった諺があり、「言葉で伝えなくてもわかるだろう」という思いや、「自分は正しいことを考えているのだから相手も当然同じような意識を持つはずだ」という考えを持つ人が多い。一方で韓国は、半島国家の宿命で周辺大陸から蹂躙されてきた歴史を持ち、色々な民族と接触する機会も多かったため、自分の考えを明確に表現し、賛同してくれる支持者を出来るだけ多く募ることに長けている。つまり、日本は攻撃的に自分の考えを表明する韓国とは真逆の事を行っている。しかし、世界の世論を取り入れるためには、当然韓国のプロパガンダ手法が有利であり、世界の中で一番重要視される米国の世論でも、団結力の強い韓国系米国人の声が大きく浸透しているのが現状だ。
――日本は今後、どのような形でプロパガンダを進めていくべきか…。
貞岡 先ず、司令塔には外務省ではなくもっと新しい発想を持った人を据えるべきだ。例えば、経済産業省や国家安全保障局などが中心となって全体計画を作り、実行部隊としては大使館を利用すればよい。また、プロパガンダの手法については、電通や博報堂などコミュニケーションツールの専門知識を持った民間の知恵を借りることも必要だと思う。現状の外務省が作成するプロパガンダの計画は、対象国と日本の現状の問題点、経緯、日本の立場などを小難しく書きあげ、その資料を該当大使館員に渡し、それを受け取った各大使館員が、それぞれ独自の切り口で実行に移すというやり方だ。そのような手法では意図する政策は全く伝わらないし、伝わらなければやる意味はない。さらに言えば、人権問題などに関してはもう少し女性を活用すべきだ。特に慰安婦問題では、河野太郎外務大臣など男性陣よりも、女性の話の方が説得力を持って聞いてもらえると思う。そもそも日本には女性の外交官が少ないが、男性では難しい部分を女性の政治家や評論家に頼ることも必要だ。そういった戦略を日本外交はもっと考えるべきだ。
――宗教や国民性を理解することも、外交には欠かせない…。
貞岡 世界の中でプロパガンダを行う際には、イスラム、カトリック、プロテスタント、トランプ政権を支える福音派など、各宗派に対するプロパガンダ戦略を考えることも非常に重要だ。それぞれの宗教に的確にアプローチをすることで、庶民の中に自然に浸透していくというケースもある。そもそも日本人でそのような研究をしている人は少ないと思うが、現実には世界は宗教で動いている。宗教をめぐっての戦争も起こっている。政教分離を頑なに唱えるのではなく、世界の中での外交戦略として、宗教を熟慮したうえで作戦を練ることは今後プロパガンダを行う上で非常に重要だ。

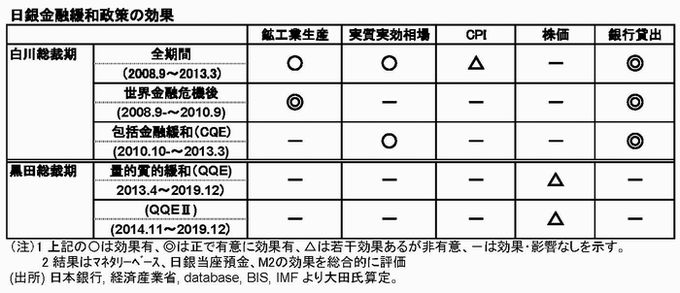
 中国は口では日中友好と言いながら、尖閣諸島の件では毎日のように脅しをかけている。そうであれば、日本も香港や台湾を支援するなど二枚舌外交が必要だ。また、安倍政権は北朝鮮の中短距離ミサイル発射について、米トランプ大統領の主張に合わせて問題ない旨の発言をしているが、日本の原子力発電所を狙われたら一体どうするつもりなのか。そういうことを勘案して日本もしっかりとした防衛網を持つことが必要であり、米国産のF35戦闘機を購入するだけではなく、ハヤブサを製造した高度技術を持つ日本の国産ミサイルを早く開発すべきだ。米国が日本を守っている限り日本は軍隊を持たないし創らないという考えのままでは、米国が弱体化した時に狼のように突然中国が日本を占領しにかかるという事をしっかり認識すべきだ。
中国は口では日中友好と言いながら、尖閣諸島の件では毎日のように脅しをかけている。そうであれば、日本も香港や台湾を支援するなど二枚舌外交が必要だ。また、安倍政権は北朝鮮の中短距離ミサイル発射について、米トランプ大統領の主張に合わせて問題ない旨の発言をしているが、日本の原子力発電所を狙われたら一体どうするつもりなのか。そういうことを勘案して日本もしっかりとした防衛網を持つことが必要であり、米国産のF35戦闘機を購入するだけではなく、ハヤブサを製造した高度技術を持つ日本の国産ミサイルを早く開発すべきだ。米国が日本を守っている限り日本は軍隊を持たないし創らないという考えのままでは、米国が弱体化した時に狼のように突然中国が日本を占領しにかかるという事をしっかり認識すべきだ。