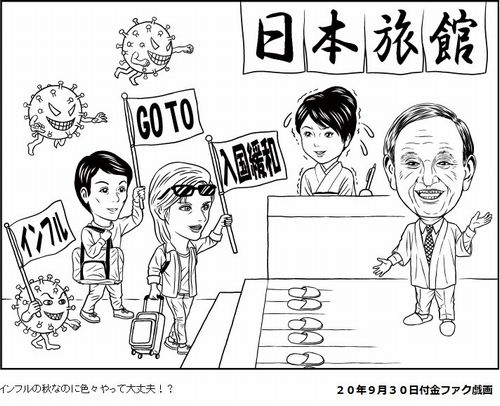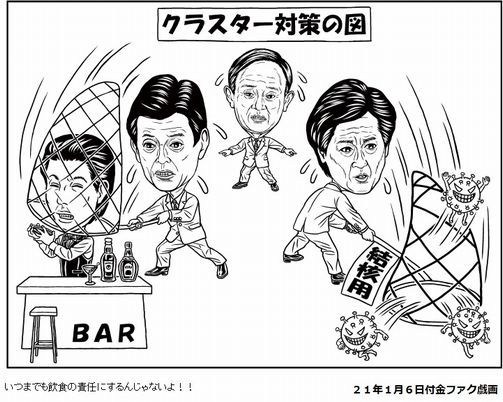――食の安全に関心をお持ちになったきっかけは…。
神山 数十年前、東京弁護士会の委員会活動で消費者団体との意見交換会を行った時に食品問題を取り扱ってほしいという要請があった。理由は、食品衛生法は読んでも全くわからないからだという。私もその時に改めてしっかりと食品衛生法を読んだのだが、実際に全く不可解であり、その後1981年10月、東京弁護士会は「食品安全基本法」の制定を提言した。それ以降、食の安全問題に取り組んでいる。食品の問題を考えるときに面倒なことは、食品の安全に関する問題は厚生労働省の管轄だが、食品表示法は消費者庁が管轄しているということだ。もともと化学的合成品の食品添加物に関しては、厚生労働大臣が人の健康を損なう恐れのないものとして指定したものに限るという制度だったが、1995年の食品衛生法改正で天然添加物を含むすべての添加物の指定制が導入された。しかし改正付則で、現に流通している天然添加物は「既存添加物名簿」に収載して使用を認めることになった。当時1000品目程あった「天然添加物」のうち489品目が収載されていたが、国会の付帯決議で「早急に安全性を見直す」ということになり、現在では350品目程度にまで減ったが、安全性の審査義務はなく、今なお、これらを使用した食品は日本国内で流通している。ただ、輸出に際しては天然添加物が使用されているという理由で米国等に輸出できないものもある。農水省ではそれらの安全性を証明しようとしているが、なかなか認められないまま今に至っているというのが現状だ。しかし、暫定措置として作られた制度ならば、期限を決めてその既存添加物リストを廃止するなどやり方はあるはずだ。そうすることで、業者としても代替できる他の添加物を探して使うようになるだろうし、外国への輸出も可能になる。曖昧にしていれば、今の状態から抜け出せないままだ。
――消費者庁が管轄する食品表示法にも大きな問題がある…。
神山 食品添加物の使用状況を消費者に伝えるのは食品表示だが、内閣府が決定した食品表示基準の原則では、使用した添加物は重量順に物質名を表示し、加工の際に使用した添加物が最終段階で残っていなければ表示しなくて良いと定められている。例えば煎餅を作るために工業用の醤油を使い、その醤油に保存添加物が使用されていたとしても、煎餅という加工食品の添加物表示には醤油に使われた保存添加物を表示する義務はない。また、消費者庁次長通知としてたくさんの例外があるのだが、その中でも一番大きな問題は「一括名表示」だ。例えば「調味料(アミノ酸等)」というように、添加物の具体的な物質名が表示されない。日本にはこのような「一括名表示」が14種類もあり、国際的にみても飛び抜けて多い。消費者庁はこの問題について消費者の意向調査を行っているが、その調査方法は、全ての添加物を細かく記したものと、一括名表示でまとめて記したものを並べて消費者に見せ、「どちらが見やすく、わかりやすいか」と設問するというようなやり方だ。当然ながら見やすいのは一括表示だろうが、内容はわかりにくい。設問自体が間違っていると思うのだが、消費者庁はこの調査で「一括表示の方が、見やすくてわかりやすいという回答が多かった」として、一切改善しようとしない。
――一括名表示になることで具体的な添加物名が消費者に示されずに、知らずにアレルギー物質を摂取してしまうというような恐れもある…。
神山 食品添加物の問題に関しては、この他にも例えば、ゼリーやわらび餅など粘着系の加工食品で、粘着の素となる増粘剤が2種類以上使われれば「増粘多糖類」という表記で良いとする「類別名表記」が認められているが、これでは何が使われているのか全く分からなくなる。香料も同様に、種類があり過ぎるが故に一括りに「香料」と表記されているが、原料によってはアレルゲンになるものもあるだろう。この点、EUでは添加物をすべて番号で表記することで、何かアレルギー反応があった時に原因を突き止める手助けとなっている。私は政府の食品添加物表示検討会にもヒアリングで呼ばれて出席したが、まったく顧みられることはなかった。消費者側委員として出席していた大多数の人の意見は、メーカー側の意見と同じだった。むしろ学校教育で添加物の危険性を教えているのはおかしいという消費者側委員が多数存在した。また、商品名で驚いたのは、「朝採りゆで枝豆」というネーミングの商品が、原料タイ産と記載されていたため調べたところ、タイで朝採った枝豆を茹でて冷凍し、輸送に約2カ月かけて日本で売られているというものだった。今、本当に日本国内で朝採って特急列車に乗せて当日販売している「朝採れ野菜」がたくさんある中で、外国産の「朝採れ」を同じくくりにして良いものか。
――日本の食品表示法が国際的にみても遅れている理由は…。
神山 食品表示法の基本理念には、「消費者の選択の権利を尊重すること」の他に、「小規模の食品関連事業者の利益に配慮すること」が挙げられている。これによって、何か表示を増やすようなことを求めても、それは小規模業者の利益の妨げになるため実行不可能だということになってしまう。もともと消費者庁食品表示企画課は農林水産省の出向者が多く、生産者側の意向が強く反映されている。牛海綿状脳症(BSE)の問題が起きた時に食品安全委員会が設置されたが、その開設準備室の室長が農林水産省畜産局出身者だったというようなこともある。これは戦犯が自分自身を裁くところを作ったようなものだ。また、吉川貴盛元農林水産大臣が鶏卵会社から現金を授受していたという問題は、国際基準であるバタリーケージ飼いの禁止を日本では例外にしてほしいという陳情だったという背景があるが、ケージによる鶏の飼育に関しては、フンによる不衛生さを防ぐために鶏に殺菌剤や抗生物質を与えるというような酷い状態が続いており、そういったケージ飼いが日本の鶏卵飼育では95%を占めている。しかもそのような状態で産まれてきた卵があたかも自然で放し飼いされているようなネーミングで売られていたりする。自然など何処にもないところで産まれてきた卵なのにおかしな話だ。
――パッケージに「保存料無添加」と書いてある商品でも、本当に無添加ではないと聞く…。
神山 「保存料無添加」と表示されていて、日持ち向上効果のあるグリシンを使っている商品はよくある。防腐効果と日持ち向上効果がどう違うのか、私には全く同じにしか思えないが、そういった嘘の表示で購買層を広げようとしている商品は多い。コンビニなどで売られているカット野菜もそうだ。次亜塩素酸ナトリウムで殺菌し、栄養成分まで一緒に抜けてしまったものを「新鮮カット野菜」として販売している。これは、加工助剤として製造途中に使用しても最終的に成分として残っていなければ表示をしなくてもよいという制度が背景にあるのではないか。他にも、食の安全・監視市民委員会で編集・出版した「かくれんぼ食品・パートⅡ」には、知らずに食べている添加物についての事例を記載している。今なお日本でまかり通っているおかしな食品表示が少しでも改善されて、国民が安心して食品を口にすることが出来るように、これからも尽力していきたい。(了)