三井住友銀行 国際金融研究所理事長
元財務官
国際通貨基金(IMF)前副専務理事
古澤 満宏 氏
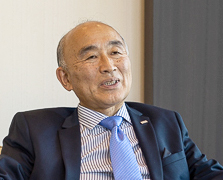
――ロシア・ウクライナ戦争が世界経済に色々な影響を及ぼしている…。
古澤 ロシアのウクライナ侵攻前の今年1月にIMFが発表した2022年の世界経済の見通しは4.4%成長だったが、4月の見直しで3.6%成長となり、相当下振れた。もちろん当事国が一番大きな影響を受けており、ウクライナに至っては、今年1月の予想ではプラス成長だったものが、4月見直しでマイナス35%となり、来年の見通しは立てられない状況にある。またロシアにおいては、今年はマイナス8.5%、来年はマイナス2.3%と2年連続でのマイナス成長が予想されている。ロシアとの関係が深い欧州は1月発表の3.9%から4月の見直しで2.8%成長となっている。日本や米国、中国の成長率は欧州ほどではないものの、資源価格高騰や世界経済全体の減速の影響から下方修正された。コロナ禍からの回復過程で昨年夏頃から物価高騰は始まっておりサプライチェーンも混乱していたが、それが改善する前に、ロシア・ウクライナ戦争によって新たなサプライチェーンの混乱が引き起こされている。これによって世界経済は全体的に減速していくと見られている。
――資源や穀物の価格高騰による食料不足で、飢餓に陥っている国もある…。
古澤 例えば、エジプトでは小麦の約8割をロシアやウクライナから輸入していたため、パン価格が高騰して国内が混乱に陥り、現在IMFに支援を求めている。また、スリランカは主に観光収入で成り立っていた国だが、コロナ禍で観光産業が大きく落ち込み、そこに今回の物価高騰で遂にデフォルトとなった。もともと途上国の財政状況はコロナの影響でかなり逼迫していた。そこにロシア・ウクライナ戦争が拍車をかけ更なる窮地に追い込まれている。資源も食糧もなく外国から外貨建てで借金をしているような国にとっては、米国の金利が上がれば自国通貨が下がり大打撃を受けることになる。そういった国はこれからも出てくるだろう。IMFが予想する今年のリスクは第1にウクライナの行方、そして2番目は社会不安だ。食料やエネルギー価格の上昇で社会不安が生じて政権が揺らぐような国には注意が必要だ。
――ロシア・ウクライナ戦争で穀物の輸入が厳しい中、自国通貨が安くなれば、穀物の購入自体が出来なくなり、国内不安はさらに広がっていく。今後の米国金利の動向は…。
古澤 米国の5月のインフレ率は8.6%と前月を上回り、まだ暫く高止まりの可能性があり、インフレに対処するため金利を上げる必要がある。IMFは来年にはインフレは落ち着くという見通しだが、暫くは高止まりの状況が続く。FRBのパウエル議長の話しぶりからすると、データを見つつ、7月も金利を引き続き上げることになるのだろう。新興国では自国通貨の防衛策として金利を上げている国は多いが、金利をあげると国内経済にはマイナスに働くため、ジレンマに陥ることもある。日本は欧州に比べればロシア・ウクライナ戦争の直接の影響は小さいが、資源価格上昇や世界経済全体の減速の影響を受けている。英米ほどではないが、物価も徐々に上がっている。世界経済全体が落ち込めば輸出も落ち込むだろう。安穏としてはいられない。
――ECB(欧州中央銀行)はマイナス金利からの脱却を宣言した。一方で日本では金利引き上げの動きは見えず海外との金利差は拡大し、さらに円安も進んでいる…。
古澤 欧州でもインフレ率が上昇し、早めに対処したいという事なのだろう。一方で日本経済はインフレ率も米・欧ほど高くはなく、英米ほど賃金が上がっている訳でもない。経済の状況が違うため、日本では今の金融緩和をまだ続けた方が良いということだろう。米国について言えば、コロナ禍によって仕事を辞めて財政支援を受けた人たちが増大し、それがなかなか戻らず労働力が不足し、賃金を上げざるを得なくなったという状況だ。日本は物価上昇も米・欧ほどではなく、賃金も上昇しておらず、状況は異なる。現在の円安を止めるために金利政策を変えるべきだという声もあるが、為替はファンダメンタルズを反映して動いている。金利や物価といった経済のファンダメンタルズが違うため金融政策の方向性が違い、そこで日米の金利差が出てくる。それは当然のことだ。現在の円安はなるべくしてなっている訳で、為替のために金融政策を変えるという考え方は妥当ではない。
――国連はロシア・ウクライナ問題によって機能しなくなっているが、IMFによるロシア制裁は…。
古澤 今のロシアへの制裁はそれぞれの国が行っているものであり、IMFとしては、ロシアがIMFのメンバー国として、IMF協定に違反するといったようなことがない限り制裁を行う理由はない。世銀やEBRDはロシアやベラルーシに対して支援を見合わせているが、今のところロシアがIMFに支援を要請するという話はなく、仮にロシアが支援を要請したとしても、理事会が承認するかどうかは疑問だ。IMFの意思決定プロセスは、加盟190カ国の出資比率に応じた発言力を持つ24人の理事で構成される理事会で議論される。融資等の通常案件は過半数で決定されるが、重要な事柄については85%の賛成が必要となる。この点、米国が16%の発言権を持っているため実質的には拒否権を持つが、機能不全に陥っているということは無い。少なくとも今の段階ではきちんと機能している。
――ロシアと同様に、今度は中国が覇権主義を掲げて暴走する危険性もある…。
古澤 中国が、商業ベースの金利で相手国に融資し、負債を返せなければ港湾等の利用権を得るといった手法が相手国の経済発展に資するのかという疑問が呈されている。中国に多額の債務を負う国がIMFに支援を要請するというケースも出てきている。この問題についてIMFのシェアホルダーは当事国の中国に対する債務がきちんと整理されていないままお金を貸すことはできないというスタンスだ。公的債務の再編を行ってきたパリクラブのメンバーではない中国等を含めて債務再編を行う枠組みは一昨年11月にG20で合意されたが、中国の協力が不十分で、まだ期待された成果をあげられていない。
――日本は今後どのように国際協調を進め、如何に中国と付き合っていくべきなのか…。
古澤 中国が巨大なマーケットであり、世界第2位のGDPを持つ国だという認識を持ちつつも、日本は今後、如何にサプライチェーンを構築していくのかをもっとしっかり考えなくてはならない。政府の指針を待ち従うだけでなく、それぞれの経済主体が各々でリスクに備える必要がある。これまでの企業行動はグローバリゼーションの中で経済の最適化という観点からサプライチェーンを構築してきた。しかし、今回のロシア・ウクライナ戦争で我々が学んだ事は、経済の最適化だけに頼っていくのはリスクがあるという事だ。実際に国連安保理は機能不全に陥り、G20での国際協調も進んでいない。それをグローバリゼーションの終焉というのか、新たな局面に入ってきたというのかわからないが、今後暫くの間はG7を核にしてQUADやIPEF、TPPといった様々な枠組みの中で協調を模索するという状況が続くのではないか。日本としてはそれぞれの枠組みで、自国の利益に合致するものをうまく利用していくということではないか。
――IMFは今年5月にSDR通貨バスケットの見直しを行い、人民元の構成比率を引き上げた。この意味するところは…。
古澤 SDR(特別引出権)の5つの通貨の構成比は5年毎に見直しを行い、基本的に米ドルの割合が一番大きいが、今回の見直しで人民元とドルが上昇し、一方でユーロと円とポンドは低下した。2016年に人民元がSDRに正式採用された際にはかなり議論になったが、貿易量や立地優位条件などからバスケットの割合が判断される中で、中国経済がさらに大きくなれば通貨バスケットの人民元の割合がさらに大きくなってくる可能性は否めない。もちろんSDRは個人が保有するものではなく、国家間の取引や国際機関で使用されるものだが、外貨流動性を供給するという意味合いはある。ドルの基軸通貨としてのポジションは、近い将来変わることはないと思うが、外貨準備の構成が調整される可能性はある。IMFにはコロナ禍から世界経済を立ち直らせるという課題に加えて、ロシア・ウクライナ戦争に起因する経済の減速への対応という難題がのしかかってきた。戦争の終結が最も重要だが影響を受けている国々を支援し、世界経済全体の回復を図っていかなければならない。(了)
